水野章二編『琵琶湖と人の環境史』,岩田書院.
が手元に届きました.
私が分担執筆した部分は,下記です.
厳しい学術書出版事情の中,すこしでも売れてくれればいいのですが...

が手元に届きました.
私が分担執筆した部分は,下記です.
厳しい学術書出版事情の中,すこしでも売れてくれればいいのですが...
むかし大学院の修士課程のとき、某、アフリカを研究していた先生に「物事は具体的に考えろ!」と指摘された。
そのことを、最近の締め切り原稿と格闘していて思い出した。
最近の自分のよくない点は抽象的な表現で、オチをつくろうという思考が支配していたと実感。他分野との議論のなかでは、方法論に関して具体的な議論を行うと、結果的に、「技術論」に終始して、細かい話題に終始するので、避けていた自分もある。
逆に、抽象度を高めた議論では、自己の認識・理解度の上に立ったオチとなるので、自己の専門外の方にとっては、理解不可能だということも学んだ。
通常、議論を継続していて、ある程度の問題意識が共有されているコミュニティであれば、それでも議論の方向性は安定するが、問題もある。
そのような時に、冒頭の指摘を思い出し、より具体的な思考にシフトしようと、今のモードではそのように感じている。
だたし、昔から抽象的なレトリックで、妄想するのは、たいへん好きで、それことが、自分の特性かも・・・・と、すこし、自分が理解でき、オトナになったような・・気も。
行ったり、来たり、さまよったり・・・のくり返し。
・・と書けば、「貧乏暇なし」。ということ。
ここ数カ月、いつも締め切りに追われて、格闘する日々。
年度末から年度初めにかけて、1)職場の各種事務処理、2)科研などの各種事務処理、3)編著本の編集や査読、事務連絡、4)新聞記事原稿、5)分担本の執筆・校正、6)一般向け短文原稿執筆修正、7)3)の自己原稿二本で、締め切りのない原稿を創ろうと意気込んでいたら、次の原稿依頼。
で、ちょっと考えたら、ここ数年の動き。一昨年は、国内学会で6件ほど発表やコーディネート)、昨年は海外の学会やワークショップで8回くらい発表で、落ち着く暇がなく、今年は発表より書くことを主体にしようと思っていたら、案の定そうなったが、今度は「デッドライン」の輪廻。
・・・とおもったら、昨年の海外調査時には、3500mをこえるヒマラヤのテントのなかで校正していたり、ブラマプトラ川の船上から原稿の校正を送っていたことも思い出した。
国内の研究会や研究の打合せで、国内出張にでかけると弁当箱(ノートPC)が当たり前になり、またネット端末も持参するようになり、どこでも仕事ができる。逆にいうと原稿を書くは、待ち時間などの喫茶店、本を読んだり、原稿の構成を考えるのは、食事時や移動中の電車やバスのなかが、集中できて、よい。
今日は、休日だが、自宅で原稿を書くことはもう当たり前になったし、先週末の古都への出張も、待ち時間にある程度の難しい問題について、原稿の作業はできた。
こういった行為は私に限ったことではない。共同研究者も海外調査時のトランジットのネットカフェで徹夜で一本の原稿を仕上げていることはママあるし、「甘えたこと抜かしたらアカン」と、自分自身、こころしているが、データをじっくりこねくりまわした論文を書くことに非常に飢えている、という感じがする。
家人には、家に仕事持ち帰って不機嫌な顔になるな!と、いつも指摘されるが、私自身最近は、このようにオンとオフを使い分ける行為そのものが自己へのストレスになると「開き直って」、「追い出し」をくらわない程度に家庭の作業もすすめる。
原稿を書くことはもちろん「自分に向き合う行為」で、精神的に「しんどい」行為だが、書きたい、いや、表現したいことがあり、その立場にいることを考えたら、甘えたことをプロとして慎みたいと肝に銘じている(たい)。
職業研究者として作品として原稿を生み出すことは、義務でもあり、喜びでもある。なにより、書くことによって、次の展開をさまざまに思考する。
・・とブログに書き留めることも、私にとっては一連の大事な行為。
写真は、高野山大学・奥山直司さん(密教の専門家)ブログ「コンタクト・ゾーン亜細亜」http://okuyama08.blog120.fc2.com/
より転載。
もう2年前以上の奥山さんらとインド北東部、アルナーチャル・プラデシュ州の調査の一コマ。
| 私の拙論はのぞいて、標記の一冊が刊行されたよう(まだ手元になく、チラシが先行して届いた)ですので、ご案内いたします。
やはり、琵琶湖周辺地域は、「環境史研究」の先端的な場であることを自覚しました。 ちなみに、私の原稿の著者校正時、初校はヒマラヤ山中の3800mのテントの中で、再校は、バングラデシュのジャムナ川の船上で、デジカメで原稿を作成し、アクセスポイントに注意しながら、メールで返信するという、「離れ業」で、内容より、そちらのプロセスが想い出深い作品となりました。 (ここから、岩田書院のWebより転載) 水野 章二 編 2011年5月刊 |
|
| 本書は2006年度から4年間、滋賀県に拠点を置く滋賀県県立大学・滋賀県立琵琶湖博物館・滋賀大学3機関の環境史に関心を持つ研究者が、科学研究費補助金を得て、共同で進めた「琵琶湖の歴史的環境と人間の関わりに関する総合的研究」の成果をまとめたものである。 文献史学・考古学・地理学・民俗学などの研究者が、琵琶湖というフィールドを対象に、そこで展開された人と自然の関係を考察し、新しい環境史研究の構築をめざした。 共同研究のなかでは文献史料や地籍図などの調査・収集も進めたが、最も力点を置いたのは、琵琶湖集水域の古代・中世集落遺跡を、刊行された発掘調査報告書 から拾い出し、それを集成する作業であり、その成果が添付CDの資料である。なお湖東地域については、整理内容を旧市町単位に文章・グラフにまとめた。 |
||
| 【主要目次】 | ||
| 序章 | 琵琶湖の歴史的環境と人間 | 水野 章二 |
| 第1章 | 遺跡の立地環境解析からみた琵琶湖周辺の環境史 | 宮本 真二 |
| 第2章 | 近江の古代・中世集落遺跡−栗太郡の分析を中心に− | 志賀 崇 草間正彦 |
| コラム | 湖東地域の古代・中世集落遺跡 | 水野 章二 |
| 第3章 | 近江国河上荘の湖岸と後山 | 水野 章二 |
| 第4章 | 中世前期の堅田漁撈 −『賀茂社諸国神戸記』所収堅田史料の紹介− |
橋本 道範 |
| 第5章 | 安土城築城期における大中の湖の湖沼環境変化 | 古関 大樹 |
| 第6章 | 近世の琵琶湖岸村落と幕藩領主 −高島郡針江村の水辺の土地支配− |
東 幸代 |
| コラム | 中世奥嶋の環境と土地利用 | 杉浦 周子 |
| 第7章 | 琵琶湖岸における逆水灌漑 | 市川 秀之 |
| 第8章 | 琵琶湖岸村落の「文化的景観」の全体構造 −滋賀県高島市針江地区の「里湖」と「里川」− |
佐野 静代 |
| コラム | 琵琶湖岸の生業と景観 −「近江八幡の水郷」の現状と課題− |
塚本 礼仁 |
| 付録CD | 近江の古代・中世集落遺跡集成 | 志賀 崇 草間正彦 |
| 湖東地域の古代・中世集落遺跡 | 国分 政子 | |
各種のデッドラインの原稿は,いまだ継続するが,自分の原稿ではなく,依頼側になったことも,さいきん,トシを感じる.さらに,依頼した責任上,責任をもって,質の向上にあたらないといけないので,他者の原稿には,自分以上の神経と,精神的な体力を使う.
・・・・・
そのような中,「ハズレ」を極力なくすために,書評を根拠とした書籍の購入を行っているが,今日,届いた本は「既視感」が.....
本人は,ある程度新鮮に読めるが,家人によると自宅の本棚の隅で,みたことがあると・・・・・・.
こういう経験は,約10年前から始まったが,活字に没頭してはじめて気づく,自分への信頼が揺らぐ,瞬間.
...というような,一日.
とにかく,文章を生み出すことは,むかしから好きで,いまも好きだが,多角的なモードを処理する技術は,いまだ未熟であると,実感する日々.
5月14日 勤務日で,1)編著本の各種原稿の確認,2)事務処理各種,3)自分の原稿の図と文献,落としどころ,4)査読依頼,5)メールの返答で,力尽きた.
5月15日 休日で,朝飛び起きて,子供を誘って,町内会の掃除.疲弊し,1時間は身動きがとれない.その後,近隣の美術館へ.3年ぶりくらいで,モノは西欧の博物館・美術館に太刀打ちできないが,そのサービスは立派だと関心.その後,買い物のため30kmくらい車の運転.鼻炎がひどくなるが,照葉樹林の「山々は笑っているような」美しい景観.深夜,すこし原稿の作業をする.
5月16日 通常の起床して,家族を仕事と学校に送り出してから,PCを立ち上げて仕事の確認.休日だが,仕事モードとなる.その後,1.5万kmを経過して劣化が激しいバイクのタイヤ交換へ.(いまの愛車も,もう10年目).午前中に終了し,帰路に買い物をして,自宅で昼食.その後,最後バイクで前日にいった場所に1時間走り(タイヤのならし),天候に恵まれすぎて,極度に疲弊する.21歳の時に,京都ー東北一周を真夏の下道で行ったが,「あの時に体力は・・・・??」と感じ入る.その後,帰宅し,たまりにたまった書類や本で埋め尽くされている書斎をすこし化かずけて,夕食のためにコメをといだり,洗濯物を取り込んだり,洗濯機を掃除したりして,子供の帰宅をまって,犬の散歩.ヒマラヤから帰った直後は,高所仕様の身体だったが,回復させるため,全力疾走を繰り返す.その後,家人の帰宅をまって,子供を乗せて,塾とジムがよい(私でなく家人)のため,車の運転.空腹で疲弊感漂う.深夜机に向かうが,睡魔が・・・・.
5月17日 勤務日.早朝仕事の研究者からのメールでいろいろ原稿の内容などを考える.その後,研究費関係の事務作業.これは間違いつつも終わったが,伝票がたまっていることは,いまは,考えないようにしている.
・・・という日々.
休日もいろいろ動いてしまうが,このような間にも日常なかなか読めない書籍をすこし読めたりする時間や,語学の勉強ができて,よい時間にしたいと思う.書店に行くと,すぐに本が欲しくなるので,さいきんは,欲しい本をみて,記憶のなかかでそれでも必要な本や,書評をみて購入しようとしているが,そうはいっても,本の山の「堆積」はすさまじい.
上の写真は,いま現在ではないが,ひとつき前くらいの研究室の一角.斜面崩壊どころではない空間だったが,いまもあまり変化していない.
こちらは,ロンブンの「堆積」がすさまじい.(私のではないところが・・・・).
研究室の机上には,職業研究者になってから大事にしている新聞の切り抜きが,色あせてはいるが,変わらず貼ってある.もう,10年以上たつ.
それは,神沼克伊(国立極地研究所)氏の「80点主義」というちいさなコラム.
この記事の正確なクレジットがいま手元にないので,ここでは記せないが,要は,100%(満点)の完成度を求める論文一本より,80点(%)の完成度の論文を継続的に書け,という内容.(ただ,80点にもっていくのも苦労するが,)
「天才は5年に一度の論文執筆で許されるが,凡人はできるだけ書け」(永田武)で,結果的に80点の論文の蓄積が,数年後には100%(点)以上の成果となる,というコラム.
その中で,「胸突き八丁」というコトバもでてくるが,さらに凡人の私は,いつも,いつも,同じ.
しかし,80点にまでもって行くためにも,多大な労力が必要で,コトバがでてこない瞬間と,さらに言えば,私の場合,「書けなくなる恐怖心」が常にあり,「怖くならないために,書き続けよう」としている.
たぶん,これは一生そうしないと,研究という行為は継続しないと,感じている.
院生時代,ある先生は「宮本.走り続けないとダメだ!」と怒られた. また,口の悪い関西出身の先輩は「論文はトイレットペーパーと同やで!」「下痢状態と同じように,出し続けないとダメなんだよ!宮本!」(トイレットペーパー理論)とご指導いただいた.
たまには,「便秘」になりたいときもあるが・・・・
私の代表の科研費はまだ継続中ですが、研究分担者として昨年度申請していた下記の課題が採択されたと通知があったようです。
歴史学(中世史)の研究者との「環境史」に関わる仕事です。
基盤研究(C)「日本中世における「水辺推移帯」の支配と生業をめぐる環境史的研究」(研究代表者:橋本道範)
季節の移行期だが、締め切りも脱稿も、「日々継続」という移行できない(しない)日々。
ということで、まったく関係ないことを妄想することも大事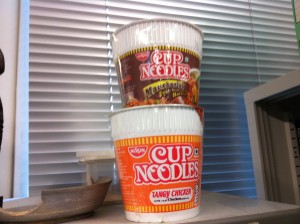 だろう。
だろう。
写真は、紛れもない日本が世界に誇るCup Noodles(カップヌードル)である。インドの北東部で、最初に出会ったのは、昨年の9月。ただし、それまでは現地ではマギーと通称される袋ラーメンが一般化しており、時間がないときの峠茶屋のような茶店では、これを食した。アフリカで流通しているものと同じブランドだったと思うが。正確ではない。
昨年の8月〜9月の調査時に出会って以降、新作がいくつか発売されているようで、変化の兆しさえある。ただし、インドでも、インドの中心部といわれるデリーやムンバイなどには、めったに出むくことがないので、この変化にも、数年の時間的差異は存在するものと思う。
味は現地の嗜好に合わせ、日本でのカップヌードルとは別物だが、現地の学生の評判によるとなかなかイケルのだそうだ。また、容器も異なる。
こういったところにもインドの「変化」を感じることができる。
・・・・・まったく関係ないお話し。
いろいろ精力的にがんばっているグループから依頼を受けて、同時並行的な原稿その1をまとめている。
通常、研究者において評価の対象としてもっともポイントが高いのが、「査読(閲読)つきの学術誌」であることは、ひろく共有されている事実だろう。
しかし、今の「困難」は、高校生以上を対象とした雑誌である。「ムラ」と称される研究者集団間では、卑下の意味を込めて「雑文」と称される方のいるが、わたしはそのようにはとらえていない。
根本的には、研究者集団という「ブラックボックス」をオープンにするべきだ、という想いがあるが、研究者の思考プロセスなども公開したほうが、科学や学問を孤立化させないためにも、大事な仕事だととらえてること。さらに、私たちの世代、もしくは以下にはこのような意識は共有されているだろし、その力量も研究者にとっては大切な行為だ。
もちろん、研究者にとって論文として成果を公表することは、義務でもあり、大事だ。
しかし、いま格闘しているのは、自らが「おもしろがっている」研究を、一般の方々を対象として1)平易な文章で、かつ、2)短くまとめること。
年度末の慌ただしさを理由に、充分な推敲を行わず、編集委員会の力量に「たよって」「あまえて」脱稿し、頭の記憶のなかからデリートしたが、「うならされる」コメントが帰ってきたのだ。
つまり、「自分のことを、自分で説明すること」で、自己の思い込みと、異分野間で共有されていない情報を、どう噛みくだいて書くか、ということ。
しかし、「自分のことが一番よく分からない」
・・・・というジレンマ。
「ん・・・・。さすがだ」というコメントと同時に、自己を見つめ直す機会を与えていただいて「感謝」だが、他のたまった性格の違う原稿と同時並行は、なかなか、「しんどい」と、相変わらず行ったり来たりの悶々とした日々が続く。(オチ無し)
写真
もう、数ヶ月前だが、都市の再開発によってうまれた「隙間」に形成されたネパール料理屋で飲んだネパールのビール。
約2年前の12月、インドからネパールに入り、底冷えするカトマンズ市内で、それも、ストライキでホテルの一室に幽閉され、原稿を書いているときに出会ったビールと日本で再会。
ただし、高いし、少ないし、日本で飲むとそれほどの感激がなく。。。店主のネパール人に「いちゃもん」を入れた。いわれなき批判で店主はこまった顔をしていたが、友だちになった。
ヘタなネパール語を話す変なニッポン人と思われているだろうが・・・